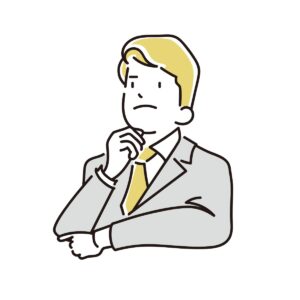目次
背景:何が起きているのか
- 沖縄県北谷浄水場では、水道水の中のPFAS(有機フッ素化合物)を除去するために「高機能粒状活性炭」が導入されています。
- この活性炭を定期的に交換・更新する必要があり、その費用を補助する制度があったものの、防衛省の米軍基地施設整備補助事業の対象外となる見込みで、2026年度以降はその補助が使えなくなる可能性があります。
- これにより、更新費用約16億円を県や水道利用者が負担する可能性が生まれており、水道料金への転嫁の可能性や、除去処理の維持が困難になる懸念があります。
今後の課題:住民の安心を守るために必要なこと
補助制度がなくなることで起きうる事態をふまえると、以下のような課題が明らかになります。これらは、安心して暮らすために、地域・行政・技術者らが共に考えるべき点です。
| 課題 | 内容 |
|---|---|
| コスト負担の透明性 | 費用がどのように水道料金に反映されるか、あるいは税金等からまかなわれるか、住民が納得できる説明が必要です。 |
| 水質維持のための資金確保 | 活性炭の更新を怠ると、PFAS濃度が上昇するリスク。安定した予算を確保できる体制が求められます。 |
| 代替技術の検討 | 活性炭以外にも、PFAS除去の技術は進んでいます。コストや対応速度・効果を比較し、有効な選択肢を検討すること。 |
| モニタリングと情報公開 | 定期的な水質検査結果を住民に公開し、PFAS濃度がどの程度かを知ること。安全性・変化の見える化が信頼につながります。 |
| 住民の理解と参加 | 情報を得る手段を増やし、住民が意見を言える機会を持つこと。浄水場見学や水道局との意見交換など。 |
| 長期的な政策・制度設計 | 補助制度に依存しない仕組み作り、予算の見通し、技術更新のためのシステムなどを将来にわたって維持できる制度設計が必要です。 |
個人としてできること・注意点
住民レベルでも、直接コントロールできる範囲でできる注意・対策があります。
- 地域の水質情報に注意
北谷浄水場のようなPFAS除去施設の運用状況や交換時期など、自治体・水道局の発表をチェックしましょう。 - 浄水器・フィルターの選定
PFAS対応のフィルターを使った浄水器を家庭に導入することで、飲み水・調理水のリスクを低減できます。 - 非常時・代替水の備え
補助打ち切りで処理が滞る可能性を想定し、ミネラルウォーターなどの代替水を一定量備蓄することも検討。 - 地域での声を上げる
水質や設備維持に関する住民説明会、自治体への意見提出など、住民としての関心を共有することで制度改善につながることがあります。
なぜこの問題は軽視できないのか
- PFASは少量でも健康に影響を与える可能性があり、長期間体内に蓄積する物質であるため、除去処理の継続性が重要です。
- 浄水設備が十分に機能しなければ、日常生活での飲用だけでなく調理や食材洗浄など、様々な経路での曝露リスクが高まります。
- 沖縄のように地下水も含めて水源が限られている地域では、水道水の安全性が生活の質に直結します。
結び:補助制度だけに頼らない“安心”づくりを
補助が打ち切られることで、PFAS除去の維持に関する責任の所在やコストが問われることになります。しかし、住民が安心できる水を使い続けるためには、「補助がある/ない」によらず、技術・制度・情報の三本柱で備えていく必要があります。